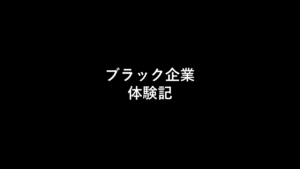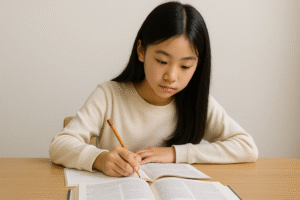25社の大企業がいかにして成功し、そして失敗していったかを紹介してくれる本です。
大企業の話となるとあまり自分に関係ないように思いますが、
盛者必衰と考えると、自分の人生も常にアップデートが必要と思わざるを得ず、
大変に学びのある本だったので紹介します。
自らの利益を守ろうとしすぎて、それが失敗を招く
この本の中で、コダックとポラロイドというカメラ関連の会社が紹介されています。
コダックはフィルムメーカー、ポラロイドはポラロイドカメラのメーカーですね。
どちらもデジタルカメラの台頭により、勢力を失った企業ですが、
この2社が、デジカメに先駆けでデジタル画像の技術を開発していた、ということに驚きました。
デジタル画像技術を持ちながら、なぜデジカメ勢力に負けたのか
ポラロイドの場合
ポラロイドは、なんと1980年台にはデジタル画像の技術を開発していたそうです。
デジカメブームが1995年ごろから始まることを考えると、
実に10年以上のアドバンテージがあったことになります。
しかしなぜ、ポラロイド社はデジタルカメラを販売しなかったのか。
それは、ポラロイドカメラが売れなくなることを危惧したからだそうです。
今既にある大きな売り上げを守るために、
革新的な技術を開発したにもかかわらず、その技術を使うことをしなかった。
そのせいで、他社がデジタルカメラを出したときに、
大きく出遅れて負けた、ということのようです。
コダックの場合
コダックもポラロイド同様に、デジタル画像技術に開発投資を行い、
実は世界で初めてのデジタルカメラを作った会社でもあります。
しかしながら、フィルム現像を大きな産業にしていたコダックは、
データをカメラ店に持ち込んで現像する、という商流にこだわります。
その結果、フォトCDという、デジタルデータ保存技術を開発し、
そのCDをカメラ店にもって来てもらう、ということに力を注ぎます。
そもそも写真を印刷することに価値を感じなくなったデジタル世代の人々が、
フォトCDに興味を示すはずもなく、倒産してしまいました。
真逆の考え方のNETFLIX
皆さんご存じのNETFLIXですが、配信事業を始める前は、何をしていたが知っていますか?
レンタルDVDの宅配サブスクリプションをしていたんです。
月額で好きな映画を決まった本数借りることができ、返却は自分の好きな時でOK、
という事業展開を行い、アメリカで大成功していました。
店舗に行く必要もなく、返却期限もない、というサービスは革新的で、順調でした。
しかし、NETFLIXは順調なレンタルサービスに加えて、新たな事業を始めます。
それが皆さんご存じの動画ストリーミングサブスクリプションです。
成功している事業があるのに、その事業を脅かすかもしれない新事業を立ち上げるのは、
そうとうに勇気の必要な決断です。
もしコダックが世界に先駆けてデジタルカメラを販売していたら
現像所との契約など、いろいろなしがらみがあったことが予想されますが、
コダックがデジタルカメラを販売していたらどうなったでしょう。
もしくは、SDカードに代わる小型の記録技術を開発していたらどうなっていたでしょう。
成功していたかどうかはわかりませんが、
少し結果は違っていたのかもしれません。
アマゾンの顧客至上主義に学ぶ
NETFLIXとコダック・ポラロイドの違いは、
顧客満足を考えたか否かだと思います。
コダックもポラロイドも自社の利益のことを考えるあまり、
顧客にとって有益なことは何か?というビジネスの鉄則が抜け落ちてしまったのではないでしょうか。
顧客至上主義を掲げるアマゾンは、
過去にトイザらスと結んでいた
「アマゾンではトイザらスのおもちゃしか扱わない」という販売独占契約を、
5000億ドルもの違約金を払って解約したことがあります。
より多くの商品を扱うためには、トイザらス以外からも仕入れる必要があったのです。
顧客のことを考えず、契約や商習慣に縛られていたら、
結果として5000億ドル以上の損失を出し、
今のアマゾンは存在していなかったかもしれません。
「顧客にとってその判断は最良か?」と問い続けるアマゾンが
ものすごいスピードで変化し続けるのは、当然のこととも言えます。
私の人生もコダックのようにならないために
実際に私の仕事も、コダックやポラロイドのように、変化の潮流にいつ巻き込まれるかわかりません。
そんな時、自分や小さな自集団の利益のことだけを考えてしまえば、
数年は利益を得られたとしても、
10年、20年という時の流れの中では、おそらく衰退してしまうでしょう。
世界にとって有益か、顧客はどうすれば喜ぶのか、ということを常に考え、
自らをアップデートし、新たな知識を得続けることでしか、
衰退を免れることはできないのだと思います。
今の成功が続くことを願うより、
小さな成功を何度も重ねていくことが大切だと、感じております。